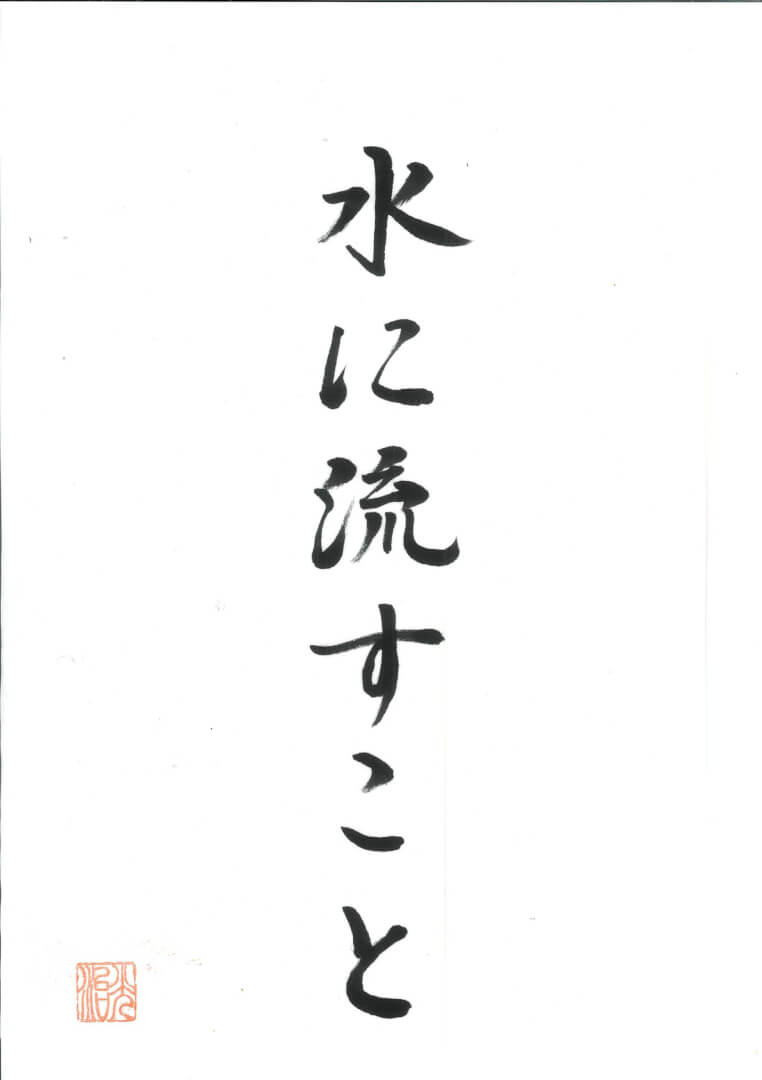
「水に流すこと」
たくさんの牛を飼う、ある信仰者は言いました。
「牛を飼うための柵(さく)の棒は
しっかりと打ち込まれており、
柵が壊れることはありません。
柵に張る縄(なわ)は、つる草で
よく編み込まれており切れることがありません。
若い牛たちでも、この縄を切って逃げることは出来ません。
さあ神様、もし雨を降らせたいならば、
いつでも降らして頂いて結構です」
(原始仏典 スッタニパータ 第1章2節-No.28)
釈尊は答えました。
「私は自分を囲う柵を牡牛のように壊し、
自分を縛る強固なつる草の縄を
巨象のように引き千切ることでしょう。
そうして、私は二度と母体に宿ることが無くなります。
さあ神様、もし雨を降らせたいならば、
いつでも降らして頂いて結構です」
(原始仏典 スッタニパータ 第1章2節-No.29)
牛飼いの生活基盤や
「誇るべき」自分の生きがいは、
* 囲う柵と、縛る縄
により、もたらされています。
しかし、釈尊は柵(さく)も縄(なわ)も壊し
引き千切ることにより、何も持たないが、
その代わりに二度と生まれて来ることは無いとします。
永遠に涅槃(ねはん:浄土)に安住するわけです。
私たちは社会で生きる為に、
* 囲う柵=会社・組織など
* 縛る縄=家族・子供・異性など
を持ちます。
そしてまた、これらが無いことが、
自分の悩みと多くの人に成っています。
そして、この項の釈尊の真意は、
* 囲う柵も、縛る縄も持つな。
と言っているのでは無いのです。
* 囲う柵を、縛る縄を持っても・持たなくても、
それに執着するな。ということなのです。
だからコノ世で大きな財産を築き、
かけがえのない家族を持てたとしても、
それに執着しない人は最高であり、死後も浄土に行く。
コノ世の財産も地位も、家族も何も無い人も、
その無いことに執着しなければ、その人は最高の世界に行く。
何もコノ世で持てなかった分、死後の浄土の歓喜とは
なおさらに大きなものと成ります。
今日もより良く生きる智慧を与えて頂いて有難うございます。
皆さんの仕合せを心より念じております。
【柔訳 釈尊の教え 第一巻】著:谷川太一より一部抜粋転載
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
