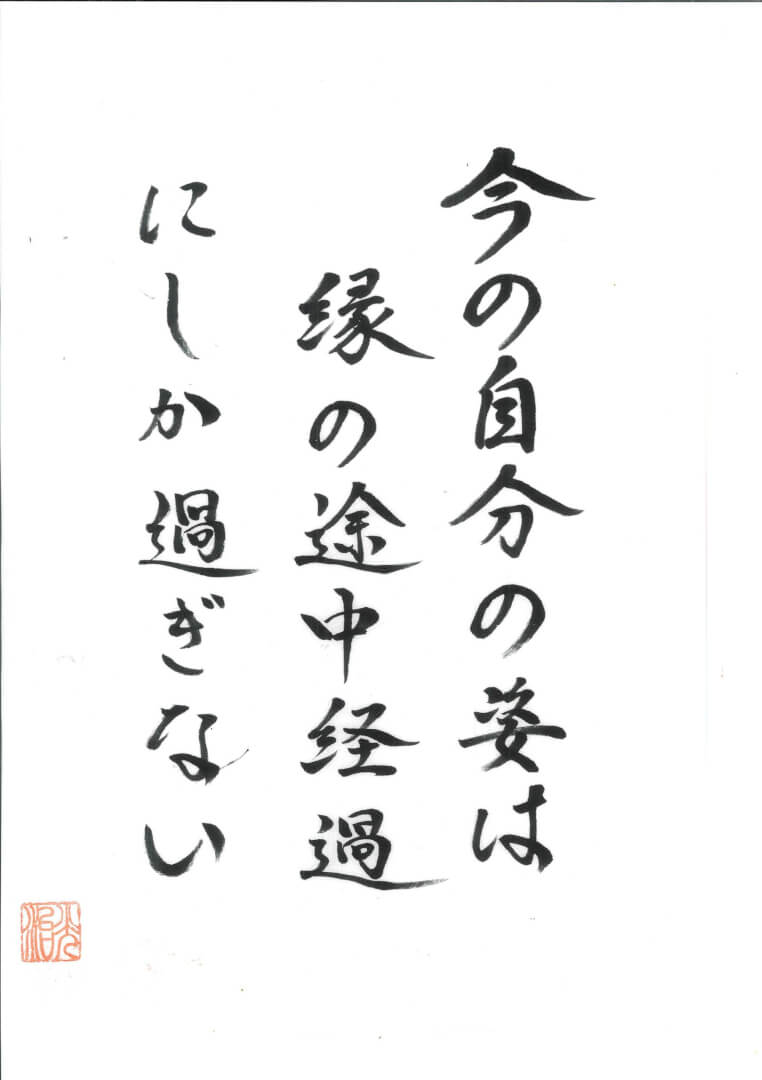
「今の自分の姿は縁の途中経過にしか過ぎない」
様々な美食をしたいという執着を無くすこと。
あちこちと、目的もなく出歩かないこと。
肉体を維持する為の、
必要最低限以上の栄養も摂らないこと。
共同生活する他の修行者たちを
托鉢(たくはつ:食糧などの寄付を他人に願うこと)で
食わせる必要は無いこと。
富裕な庶民の家に憧れることがないこと。
このようにしながら、
どんな交わり、集団の中に自分が居ましても、
自分一人で歩く覚悟を持ちなさい。
まるで1本角(ツノ)が立つサイのように一人で歩みなさい。
(原始仏典 スッタニパータ 第1章3節-No.65)
釈尊は、生まれながらにして王子でした。
若い頃には、世のあらゆる贅沢も、美しさも、喜びも味わい
尽くしています。
だからこそ、その全ての「限界」も「虚しさ」も、
徹底的に体験として理解したのです。
だからこそ、逆に、
それらへの執着を手放すことができたとも考えられます。
もし一度も贅沢を味わったことがない人が、
他人の贅沢をずっと見続けて育ったなら
心にどんな感情が湧くでしょうか?
本当に「執着を断つ」ことは簡単ではないでしょう。
私たち一人ひとりが、
なぜこの性格なのか、なぜこの心の癖なのか。
なぜ同じものを見ても人によって感じ方が違うのか。
それは、今生だけでなく、過去生の積み重ね=縁が違うからです。
だから、
-
執着を断ち切れる人
-
なかなか断ち切れない人
その差が出るのは当然なんです。
悟りでさえ、縁によって開かれる。
これは決して悲しいことではありません。
むしろ、
「今の自分の状態は“失敗”ではなく、“縁の途中経過”にすぎない」
そう気づいたとき、
私たちはようやく、自分を責めるのではなく、
自分を大切にしながら進む道を歩めるようになります。
昔の修行者も、今日の私たちも、
同じように悩み、葛藤し、比べ、揺れながら生きています。
釈尊のように、一度で全ての執着を捨てる必要はありません。
ただ、
-
“ああ、自分にもこういうサガがあるんだな”と気づくこと
-
“これは手放してもいい欲だな”と少し離れて見ること
-
“この縁は、きっと次の成長に繋がる”と信じること
これだけで、仏道の一歩を歩んでいるのです。
そして、
人間味ある悩みこそが、悟りの土台になる。
釈尊も、修行者も、そして私たちも、
同じ道の上で迷い、そして気づき、智慧を学びながら生きているのです。
今日もより良く生きる智慧を与えて頂いて有難うございます。
皆さんの仕合せを心より念じております。
参考文献【柔訳 釈尊の教え 第一巻】著:谷川太一
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
