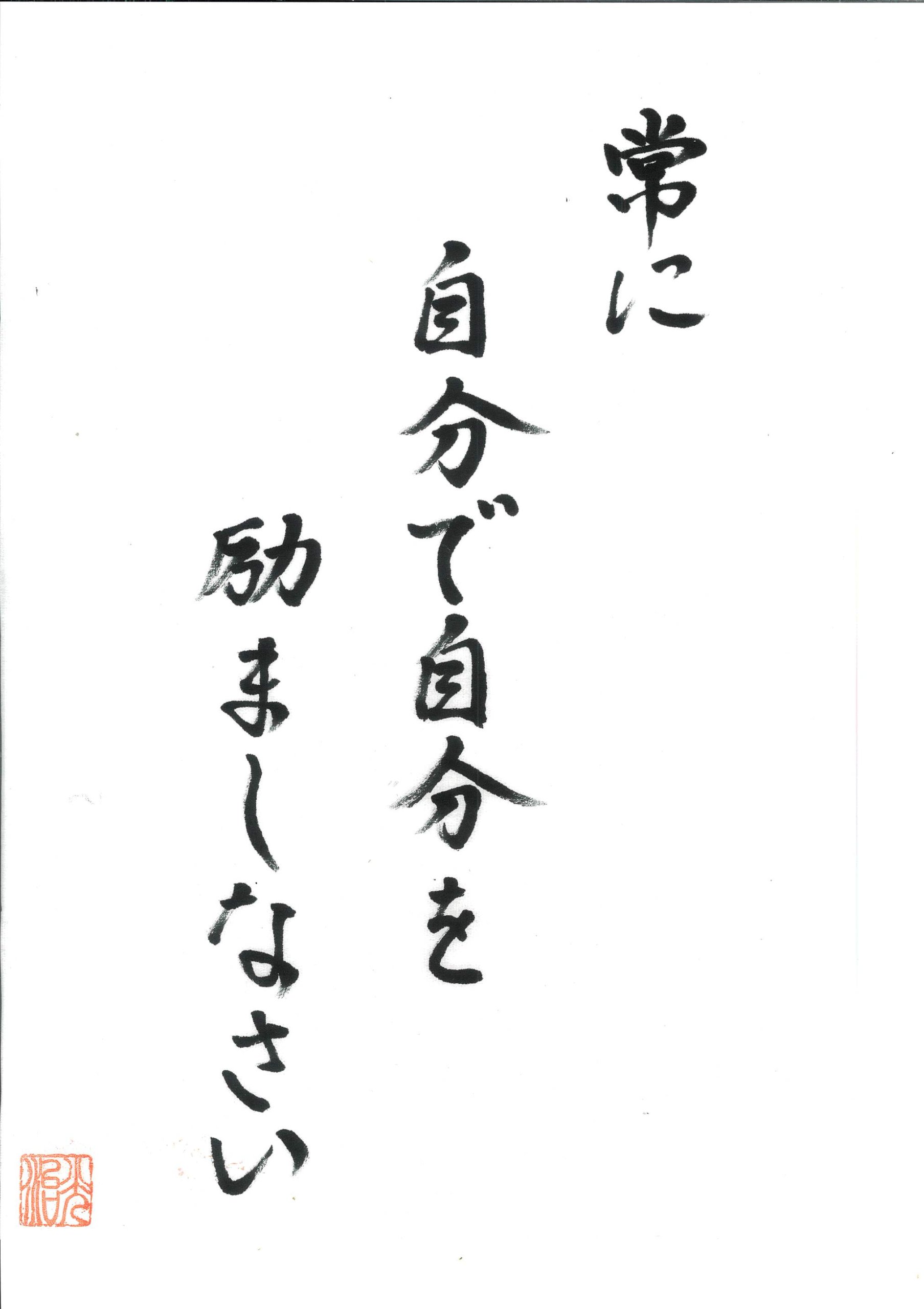
「常に自分で自分を励ましなさい」
人間は、自分で自分自身を励ましたほうが良いです。
そして、自分で自らを反省させることをしたほうが良いのです。
生きる人々よ、自分で自分自身を守りなさい。(自分をイジメるな!)
そして、正しい思いを持つように務めましょう。
そうすれば、誰もが浄土に行けるのです。
(原始仏典 ダンマパダ25章-379番)
釈尊が、またまた斬新なことを仰っています。
(1) 「自分で自分を励ましなさい!」
これは過去の自身のトラウマの視点からも、意味が有ります。自分の名前
を呼んで、「◯◯よ、頑張れ~」「まだまだ行けるぞ」「そこは注意だ」
「自分は、そんなもんじゃ終われない!」・・・・などなどと。
エベレスト山などへの登山家のエピソードを読みますと、高所に行くほど
酸欠が進み、低温と合わせていよいよ「死」を間近に多くの人間が感じる
そうです。
段々と生活のことや他人への思いが消え始めて、自分自身との対話が始ま
るようです。
その時に多い現象が、斜め上方向から別の自分が、まさに上記のような
「◯◯よ、頑張れ~」と話しかけてきて、別の自分との対話が始まるのです。
その別の自分は、以前から良く知っているような懐かしさをも持つようです。
その別の自分は、雪で隠れた危険な足下も薄れ行く意識の中で教えてくれる
そうです。
(2) 「定期的に、自分で自分を反省させなさい」
このような習慣を持つ人は、人生を無難に安定させることが出来ます。
災難を除けることにも成ります。お祓いや厄除け祈願よりも、
本当に実践的に実現させます。
今日の寝る前に、
* 今日1日の反省をすること。
* そして大事は、それでも生かされたことに感謝をして゛置く゛こと。
この2点の継続は、強力に明日からを変えて行く原資と成ります。
(3) 「自分で自分自身を守りなさい」「自分をイジメるな!」
多くの人は、自分を精神的に守るどころか、逆にイジメることで何かの
昇華をしています。これではダメなのです。運気が落ちて行きます。
イザという時に、本当の自分(良心・仏性)が助けてはくれないのです。
「今さら何言ってる!!」ということになります。
だから、普段から自分で自分を励まし、自分を虐めないで、自分の意識
を育てるのです。意識の大きい人は、他人に安心感を与えます。それは、
本人が自分の生活で育てた、その人の意識の強さと大きさの影響なのです。
自傷行為をするような人の意識は、物凄く委縮しており、他人に違和感
、冷たい感じ、心配心を起こさせます。その人のソワソワ感やイライラ
感は、他人にも伝染するほどです。
(4) 「正しい思いを持つように務めなさい」
これは釈尊が、悟り(涅槃感覚)に至るために必須とした、八正道(はっ
しょうどう)の中の1つである、重要な「正思(しょうし)」のことです。
やはり生きる間の糞袋(くそぶくろ:一休禅師は人間をこう表現しました)は、
常に自分で「正しい思考」を心掛けるべき生き物なのです。
思考はいつも、逃避、暴走、虐待、差別、色情へとネガティブへ勝手に進む
「生き物」だと思っても良いです。
定期的に、自分の思考に「中立・中道」「常識」「道徳」という手綱を付けて
引っ張ることが大切です。
このような肯定的な釈尊の智慧を毎日読むだけでも、継続する筝によって
思考が神仏の方向へと正されていきます。
釈尊は、以上の4つを「継続した」者は、浄土(涅槃・ねはん)に行きます、
と断言されています。これを信じて見ましょう。
実践が自分に教え、心からの安心と共に先行きを導きます。
今日もより良く生きる智慧を与えて頂いて有難うございます。
皆さんの仕合せを心より念じております。
【柔訳 釈尊の言葉第一巻】著:谷川太一より一部抜粋転載
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本人の道徳心
「グッド・ルーザー」
負けたのなら敗者らしく堂々としていればいい。
十分に戦ったのなら、
何も卑下することなどない。
昔から勝敗は時の運という。
勝つ時もあれば負ける時もある。
負けたからといって
相手を恨むのはナンセンスだ。
負けたら潔く負けを認めて降参すればいい。
ただし、前提がある。
それは自分の言い分がある時には
徹底的に戦わなければならないということだ。
しかし、戦って分がないとわかれば、
変に意地を張らずに潔くあきらめる。
これが英語でいうところの
グッド・ルーザー、
負けても怒ったりしょげたりしない人になれ、
という思想だと思うのだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今日の諺 「牛飲馬食(ぎゅういんばしょく)」
【意味】
とてもたくさん飲んだり、食べたりすること。
牛が水を飲むようにお酒などをたくさん飲み、
馬がえさを食べるように物をたくさん食べるという意味。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
